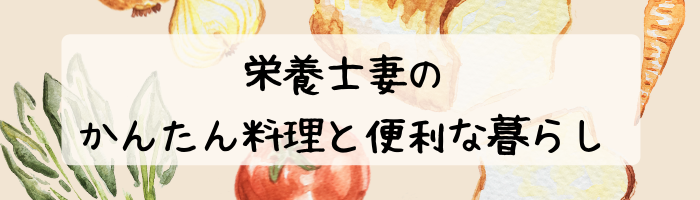巻きすの使い方はどっちが裏表なんでしょうか。
また、伊達巻や卵焼きに模様を付ける時に逆に使うって本当?
使う向きについても解説いたします。
巻きすの使い方はどっちが裏表?

巻きすの使い方ですが、実は裏表は決まっていません。何を巻くかによって、裏表が決まります。
太巻き(巻き寿司)の時は凸凹してない、平らな面に乗せましょう!
1年を通して、伊達巻よりは巻き寿司を作ることが多いので、平らな面に海苔を乗せて巻くことが一般的です。
面を、両面よ~く見てください。平らな面と、丸みを持った面があることに気が付きます。

面によって作りが違うからよく見て!

ここで言ってるのは、太巻き用の巻きすのこと。細巻き用は違います。
こちらは大きめでしっかりした造り。ご飯やのりがはみ出ず、巻きやすいです。
太巻き用と細巻き用の巻きすの違いについてはこちらにまとめてあるのでご覧ください。
http://remimari.com/archives/4054
伊達巻や卵焼きに模様を付ける時「逆」に使う

先ほど、「何を巻くかによって、裏表が決まる」と書きましたが、伊達巻や卵焼きに模様を付ける為に巻く場合は、太巻きの使い方とは逆に使います。
今度は、丸みを持った面に置いて巻きます。
これは、伊達巻や卵焼きに模様を付きやすくするためです。
伊達巻に模様が付いているのは想像できると思いますが、卵焼きやだし巻き卵にも模様を付けると、料亭やお店のようになって見栄えします。

卵料理を作る時に、白身がなかなか混ざらなくて困ることありますよね。卵の白身がよくきれるスティックがあります。
伊達巻、卵焼き、ドレッシング作りにも使えます。
私は初めて伊達巻を作ったときに、うっすらとしか模様が付かなくて、理由がわからなくて困ったことがあります。
わからないまま、卵焼きも同じことをしましたが模様は付きませんでした。
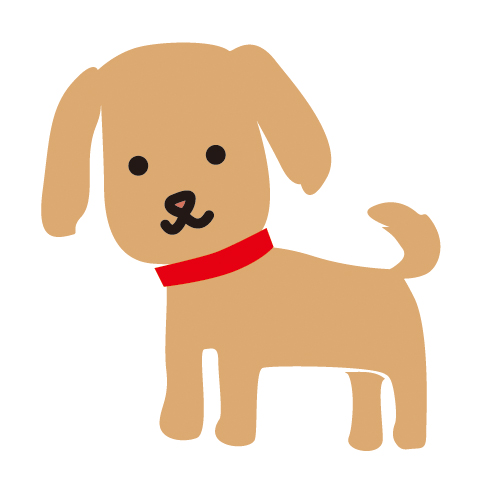
せっかく作ったのにショックだよね~
しばらくしてから、裏表逆に使っていることがわかり、スッキリしたものです。太巻きと同じ、平らな面で巻いていたので、模様が付かないのは当然のことでした。

せっかく作るのですから、失敗したらもったいないです。覚えておいてくださいね。
巻いた後に、巻きすの隙間にご飯や卵液がついて、落ちにくくて困ることがあります。巻きすの洗い方のコツについては、こちらをご覧ください。

ちなみに、伊達巻も卵焼きも、熱いうちに形を整えながら巻いて、両端を輪ゴムで止めて冷ますと綺麗な模様が付きます。簡単なので是非お試しくださいね。
巻きすの向きはどっちが前?

巻きすに向きがあるのってご存じですか?
細い竹を紐で1本1本つなげてあるのですが、最後の結び目が絶対にあり、そこだけは紐が出ていて、結び目が見えるような状態です。
その紐の結び目を手前に置いて巻くと、巻き込んだりしてとても巻きにくいので向こう側に置き、結び目がない方を手前に置いて巻きます。
※文頭の写真参照。
私は何度か使ってから気が付きました。新婚時代のことですが、なんか巻きにくいな・・。とは思っていましたが、理由まではわかりませんでした。
そんな自分のような方が、一気にお悩みが解決するといいなと思い、この記事を書きました。
情報がまとまっている方が、良いですよね。
巻きすの裏表は決まってない!巻くものに合わせて選んで使って

巻きすの裏表って絶対あると思っていたんですが、そうじゃないんですね。
作るもの、巻きたいものに合わせて使うのが、正しい使い方です。
表とか裏とか面倒で、とにかく巻き寿司を綺麗に巻ければいいという人には、プラスチック製もあります。
ご飯がこびりつかず洗うのが楽です。カビませんし保管も気を使いませんね。
特に巻き寿司でいつも苦戦する人は、早めに揃えておくと安心です。
好みの巻きすで、巻き寿司、伊達巻、卵焼き、だし巻き卵等試してみてくださいね!
【関連記事】